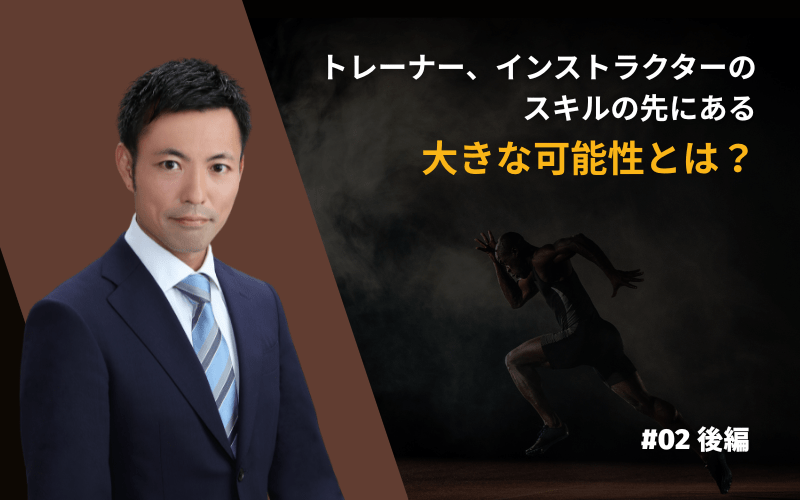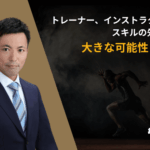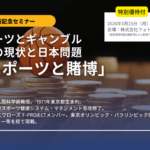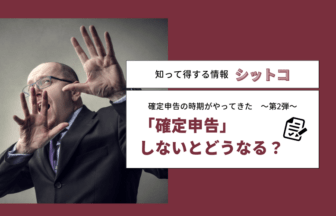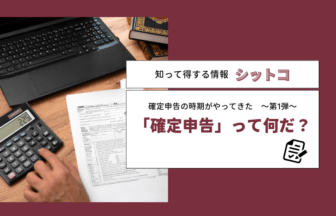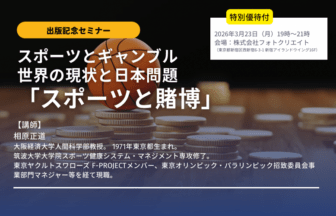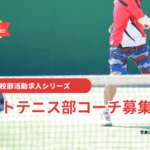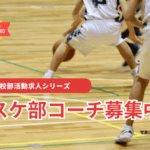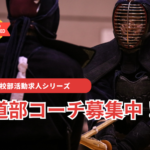インタビュアー
内藤北斗(イントラワークス運営企画担当)
今回は、日本国内においてサプリメントのための第三者検査・認証に関わる事業を行うLGC Japan Limited代表の新城南平氏に自身の経験を元にトレーナー、インストラクターが持つスキルの可能性について話を伺いました。

ーこれまで様々なキャリアの中で記憶に残ってる出来事は何かありますか?
(新城氏)
最も記憶に残っているのは、フィットネスクラブで働いていた頃、初めて管理職になった時の手痛い失敗と、そこからの学びです。当時、現場のトレーナーとして成果を出していた私は、ある店舗の責任者に抜擢されました。しかし、そこで『現場で優れた“プレイヤー”であることと、優れた“マネージャー”であることは、全く別のスキルが必要だ』という現実に、わずか1ヶ月で直面することになります。プレイヤーとしての成功体験が、逆に視野を狭めていたのです。チームを動かし、組織や施設を管理するという視点が全くなく、結果は全く伴いませんでした。
幸いにも、会社が再挑戦の機会を与えてくれ、優秀なマネージャーの下で1年間、いわば『マネジメント修行』のための期間をいただきました。PL管理やマーケティングといった知識はもちろん、大きな学びは『自分が出来ることは想像以上に小さく、チームとして出来ることは想像をはるかに超えて大きい』という事です。
その後、再び店舗の責任者としてチャンスを頂き、学んだことを実践した結果、苦しみながらもしっかりと結果を残すことができました。この経験が、私のキャリアの大きな転換点です。(苦笑)
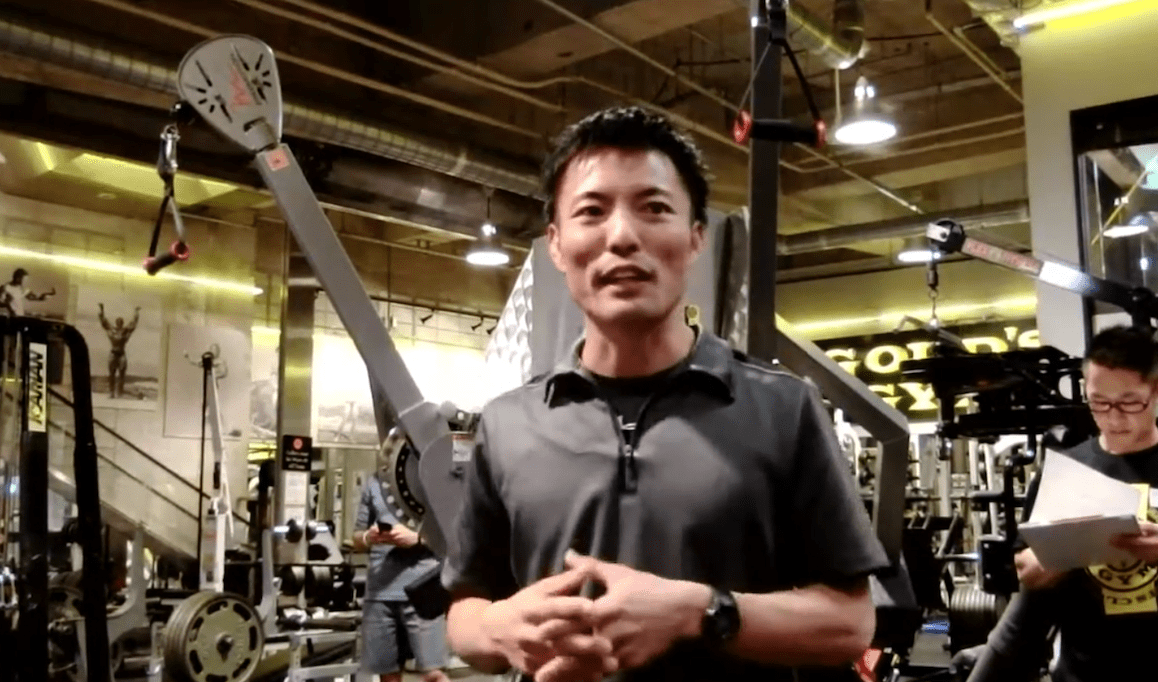
ーそこからどのような学びとか気づきを得ましたか?
(新城氏)
まず大前提として、現場上がりの私はPL管理や『ヒト・モノ・カネ』といった、いわばビジネスの『汎用的なスキル』を学ぶ必要がありました。自分に欠けていたスキルであり、大いに成長を助けてくれたと思います。その意味では、フィットネスクラブのマネジメントは、最高に良いトレーニングの場でした。様々な雇用形態の方々と共に、非常に多くの設備を維持・管理し、性質の異なる複数の売上を日、月、年で追いかける。この色んな意味で複雑な環境は、ビジネスパーソンとして非常に良いトレーニング環境を与えてもらったと今でも思います。
そして、その中で得た最大の収穫は、新たに学んだビジネスの視点と、培ってきたトレーナーとしての専門性を、決して対立させないという姿勢です。マネジメント的なビジネス視点と現場の専門性はしばしば対立しがちです。しかしこの二つのベクトルを調整し掛け合わせることで、チームとしても個人としても大きな推進力を得られること。その重要性に気づけたことが、何よりの学びでした。
ーその学びのために、何か普段から意識していたことはありますか?
(新城氏)
端的に言うと『余力(よりょく)を意図的に作り出す』という習慣です。
例えば、社内向けの資料作成や数字管理といった業務は、可能な限り効率化・自動化します。もちろん、これらの業務の重要性を否定するわけではありません。しかし、時間は有限です。そうした事務的な作業に使う時間を圧縮し、生み出した『余力』を、集客やサービス改善といった『有益な仕事』と、社外から新しい知見を得るための『自己投資』の二つに充てるように意識しています。
ーその後、どのようなキャリアを歩んできたのでしょうか?
(新城氏)
キャリアの話となると所属企業と職種の両方の説明が必要になると思いますが、比較的転職回数が多いので、簡単に時系列で紹介するとフィットネスクラブ(トレーナー兼マネージャー)の後はフィットネス機器の販売会社(マーケティングとブランディング)、人材派遣の会社(TOKYO 2020のスポンサー業務)、医療・介護・保育の事業会社(新規事業)、経営コンサルティング会社(新規事業)、そして現在のライフサイエンス企業(日本支社設立と運営)という流れになっています。転職経験以外でも、途中で2つの会社に所属する兼業社員という経験もしましたし、働きながら大学院の修士課程で学ぶという比較的珍しい経験もしています。
ーこれまでの転職活動で大事にしてきた軸は何ですか?
(新城氏)
『人の身体や健康に関わる』という軸は不変です。ただ、その中でのスタンスは大きく変化しました。
当初は、私も専門知識を突き詰めるスペシャリストを目指していました。その道は非常に尊いと、今でも心からリスペクトしています。
しかし、業界を俯瞰した時、専門性を追求するあまり視野が狭くなった専門家と、現場への理解が浅いビジネスパーソンとの間にある種の『対立構造』が散見されることに気づきました。
私は、その両者の間に立ち、双方の言語を理解し、事業を前に進めることができる『専門性も理解した、強いジェネラリスト』になりたい、と強く思うようになったのです。私の多様なキャリアは、この役割を担うための、意図的な選択の結果です。
ー転職活動で工夫していたことは何ですか?
(新城氏)
私は、転職を『イベント』ではなく、継続的な『キャリアマネジメント』の一部だと捉えています。そのための重要な習慣が、転職の意欲に関わらず、1~2年に一度は信頼できるエージェントやヘッドハンターと面談をしてキャリアの『健康診断』をすることです。これにより、自分を客観的に把握したり、世の中の状況把握も容易になりますし、何より自分の情報を第三者に預けることで、世の中になかなかでないお話が来ることもあります。
この習慣のもう一つの利点は、転職ありきで動いているわけではないため、現職の仕事がおろそかにならない点です。矛盾しているかもしれませんが、お世話になった会社に極力迷惑をかけないように動くのも大切だと考えます。

ー今後のキャリアの目標は?
(新城氏)
抽象的ですが、これからも健康産業というフィールドのどこかで、社会に貢献できる仕事をしたいです。
ー最後にキャリアを考えている人にメッセージをお願いします。
(新城氏)
トレーナー、インストラクターという仕事は、人々の健康に貢献でき、多くの感謝もいただける、本当にやりがいのある素晴らしい仕事だと思います。ただ、日々の業務の中で、その価値を見失ってしまう瞬間があるかもしれません。
他業界と比べれば、報酬や待遇といった目に見える部分で、発展途上という課題があることは否めません。
でもやはり、一歩引いて考えると見落としがちな素晴らしい点がたくさんあります。
ほんとに些細な一例ですが、カフェでも飲み会でも、人が集まれば、『健康』や『身体』の話題は、誰もが関心を持つ鉄板のテーマですよね。そして私たちは、そのテーマのど真ん中に四六時中いるわけです。
それはつまり、自分の手の届く範囲にいる人々の人生に、大小なりともダイレクトなインパクトを与えられる、ということです。こんなにも人の根幹に関わり、直接的に良い影響を与えられる仕事は、世の中にそう多くはないと思います。
その特別な価値は、仕事中だけでなく、私たちのライフスタイルそのものにも宿るのだと思います。健康を体現する専門家として、日々の暮らしそのものが、私たちの言葉に説得力と深みを与えてくれる。この仕事は、単なる職務を超えた、一つの『在り方』を示せる、数少ない職業なのかもしれません。
この業界に従事してくださる方が増えれば増えるほど、世の中が健康にポジティブに前進する可能性が高くなると思います。日々の仕事の中にたくさんの喜びを見つけながら、楽しんでキャリアを歩んでほしいと心から願っています。
新城氏のインタビューを終えて、特に印象的だったのは内容が・・・トレーナー・インストラクターという仕事は自分で様々な情報を収集して、自らで実行してならまだしも、クライアントを分析して最適解を提供し、相手の実行を支援して結果を導いていくことは、高いヒアリング力やマネジメント力が必要とされるじゃないですか。
こうしたことを日常的に実務を通じて培っているトレーナー、インストラクターは、社会においてハイスキルの人材と言えると思います。
様々な文献だったりエビデンスデータを収集して、それぞれのクライアントに対して最適解を提供する。
言語化できない抽象度が高いものものを理解してコミニュケーションをとるなども含め、網羅的に社会人基礎スキルが高いというのを感じています。
健康産業の主役として、ますます社会的注目度も役割も増していくトレーナー・インストラクターが備え持つスキルの可能性というのは他のどの業界職種においても必要なコアスキルだと述べている新城氏。
ご自身の活躍が示す通り、トレーナー・インストラクターの可能性を体現し、最大化している姿はキャリアを考えている人にとっての一つのロールモデルでもあると言えるでしょう。
▶︎詳しくはこちら(LGC JAPAN)